| ★序章はこちら→ |
| 冬の日暮れは早い。 薄い茜色を背景に、影絵のように、黒く浮かび上がる街並み。 ブルーグレーの雲が、刷毛で描いたように、西の空に流れている。 冷たい木枯らしがさっと吹き抜け、落ち葉を舞い上げていく。ジョーは思わず首をすくめた。 寒くなどない。なのに、ついつい条件反射で、そんな行動をとってしまう自分が滑稽だ。でも、今はとても笑う気分ではなかった。 そう、島村ジョーは、珍しく腹を立てていた。 (なぜ僕がここで、こんなことをしてなきゃいけない?) 人ごみの嫌いな彼が、クリスマスイブに浮かれる街の雑踏にわざわざ繰り出したのには、ちゃんと理由があった。 (僕は、フランソワーズのことが心配だから、だから・・・) あのケーキ屋に行った。彼女の仕事が終わるまで、そばにいて待っているつもりだった。不埒な振る舞いをする奴でもいたら、叩きのめす・・・わけにはいかないが、少なくとも自分がそこにいれば抑止力にはなるだろう。そう思っていた。なのに今、彼はひとり、こんなところにいる。鮮やかなサンタのコスチュームに身を包んで。 結局、ジョーは、あの3人にまんまと丸め込まれてしまったのだ。 「俺たち、今日は免許証持ってきてないからよ、お前しか行けねえだろ!」 「ま、そういうことだ。衣装もそのままでいいしな。頼んだぜ、ジョー!」 「僕も店を空けるわけにはいかないからね。これがリスト。1つ1つ丁寧に配達してよ。あ、それから!ちゃんと演技してよね。子どもたちの夢を壊さないように気をつけて!それがうちの店のウリなんだから」 赤い車体に白いバンパー。ボディに描かれたサンタと樅の木のイラスト。ジョーの運転する派手な軽ワゴン車は、クリスマスイブとはいえ大いに人目を引いた。 渋滞する市街地を、どうにかこうにか脱出し、郊外の住宅地を一軒一軒回る。思っていたよりずっと時間がかかるし、気を使う。箱を傾けたりしたら大変だ。 クリスマスイブの午後。 ケーキを届けたどの家も、幸せなオーラに包まれているようだった。扉には手作りらしいクリスマスリース。庭の木にも電飾がつるされ、華やかな光が瞬いている。 ちょっと気後れしながら、チャイムを押した。パタパタと足音が近づき、勢いよく開かれるドア。その途端、あたたかい空気といい匂いが流れ出してくる。 「わああああいい!サンタさんだ!!」 ケーキを渡すジョーの姿に、どこの子どもたちも無邪気な歓声を上げた。 「メリークリスマス!!」 拓人の指令どおり、サンタになったつもりの台詞を忘れずに。これで25軒目。最後の一箱を配達し終えた時には、あたりは薄暮に包まれていた。 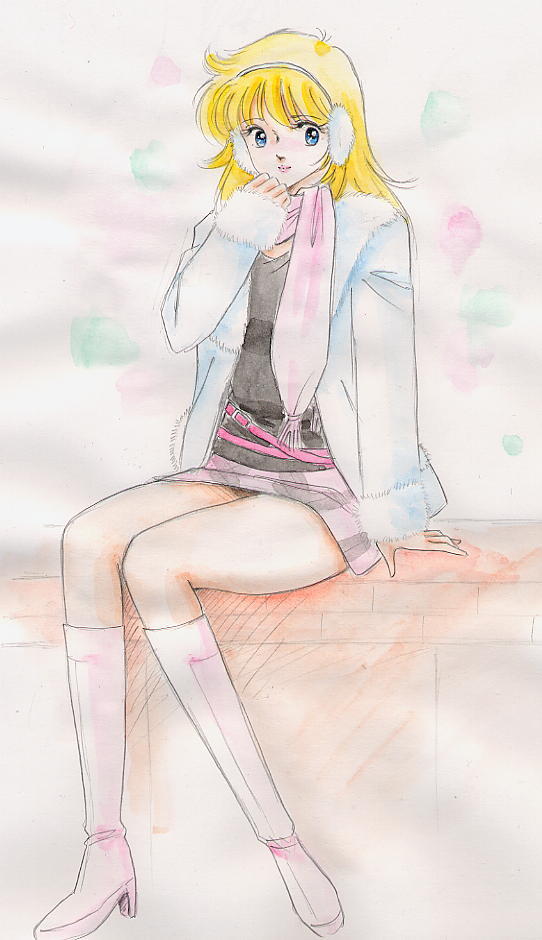 「ええっ?!!!友達って・・・男だったのか?!!」 今日の朝、フランソワーズに連れられて件のケーキ屋に足を踏み入れた途端、顔を合わせた男4人は同時に叫んだ。 もちろん、そのうちの3人は―――ボディーガードよろしく、フランソワーズに付き添ってきた―――ジョーと、ジェットとアルベルトだ。 そして問題の4人目。このケーキ屋の息子、拓人。フランソワーズと同じバレエ団に所属しているという。 (男?コイツが・・・フランソワーズに、あんな格好をさせたのか!?) 思わずジョーの眉がキッと上がる。 ぴったりボディーフィット。脚線美もあらわなサンタドレス。ケーキの予約を取るために、撮影会まがいのことまでやって。しかも調子に乗って、ケープまではずさせたというじゃないか!あの真っ白い華奢な肩を気安く人目に晒すなんて、まさに冒涜行為だ!ジョーの胸に沸々と怒りが込み上げてくる。 (いくら舞台衣装で、肌を出すことに慣れているっていったって・・・) フランソワーズだって「嫌だって言ったのよ」と言ってたじゃないか。それをコイツが無理やり・・・。そう思うと拓人の顔を見ているだけでムカムカしてくる。 初対面の人間に、これほど不快感を持ったのは初めて、だ。 当然、ジョーのそんな気持ちは、相手にも伝わっているだろう。 4人の間に流れる、何となく不穏な空気。 それを敏感に感じ取ったフランソワーズが、ちょっと当惑した顔で3人を拓人に紹介しはじめた。 「こちらが、ジェット。それから、アルベルト。そして・・・」 一瞬、ジョーの顔を見上げ、小さく微笑んでから言葉を続ける。 「彼が・・・ジョー、よ」 ふうん、とつまらなさそうな声で返事をすると、拓人は、ジェット、アルベルト、と品定めするようにゆっくり眺め、そして最後にわざとらしくジョーに視線を移し、小さく肩をすくめた。 「男・・・ね。じゃあ・・・このコスチュームは着られないよね、さすがに」 どうやら拓人は、フランソワーズの連れてくる友人3人―――当然、可愛い女の子だと思って―――にも、ミニスカサンタのコスプレをさせようと目論んでいたらしい。 「誰も見たくないもんな、男の生脚なんてさ。でも、困ったなあ。普通のサンタの衣装は、1つしかないんだ。あとは・・・トナカイの被り物と、雪だるまの衣装だけだし・・・。かといって、そんな普通の格好で店に居られても、はっきり言って邪魔なんだよね」 しばらく腕を組み、3人の男連中をじっと見つめていたが、また肩をすくめてこう言った。 「ま、いいか。じゃ、そこのオジサン、この雪だるま着てよ!」 ―――オジサン、だと? アルベルトの目が、鋭く光る。だが、拓人はおかまいなしで、スノーマンのコスチュームを彼にどさっと投げつけた。 「それから、トナカイは、アンタだ」 「え?俺がトナカイか?何だよ、これ!!こんなぬいぐるみじゃ、せっかくの俺様の顔が見えねえじゃねえか!おい、そのサンタの衣装、よこせよ!」 「サンタは―――君」 唇の端に微かな笑みを浮かべ、拓人はジョーに赤いサンタスーツを渡した。 「さあ、さっそく仕事してもらわなきゃ。これから、戦場みたいな忙しさだ。見ただろ、あの行列?」 「えっ??あの・・・とぐろまいてる行列って・・・この店の・・・?」 てっきり近所のパチンコ屋が新装オープンするんだと思ってたぜ、とジェットは目を丸くした。 「そうさ。当日販売用の整理券を手に入れるために、昨日の夜から並んでる人もいるんだよ。どんどんさばいていかないと、大混雑になってしまう。さ、フランソワーズ、早くロッカールームで着替えてきて。オジサンたちはその辺で、適当にやって」 拓人はフランソワーズの手を引っ張って奥へと姿を消し、憮然とした表情の男3人がその場に残された。 (やっと・・・終わった) 車を止めた場所への近道のつもりで、ジョーは住宅地の中にある小さな公園を突っ切ろうとした。 藤棚、砂場、ジャングルジム。もう誰も居ない。風が揺らす無人のブランコに、つい目が止まる。 不意に、小さい頃のことを思い出した。 そうだ。いつもこんな景色だった。 日が西に傾き、ぽつぽつと家々の灯が瞬き始めると、1人、また1人と、子どもたちは家に帰っていった。そして―――空っぽになった公園で、1人ブランコをこいでいた自分。あの時は、その方が気楽だった。誰かと一緒にいるよりも。けれど、今振り返ってみれば、それは何て哀しい光景だろう。ましてや、そうやって1人でいることを、淋しいとも思わなかったなんて。 でも本当は、思わなかったんじゃない。思っても仕方ないとあきらめていただけだ。涙も、哀しみも、全部押し殺して、心の奥底に封じ込めて。 だからこそ、その反動のように、時々どうしようもない衝動に突き動かされた。自分でもコントロールできない怒り。そんなものが湧き上がってきて、彼を駆り立てることがあった。かなわないとわかっている相手に、ムキになって突っかかって、そして傷ついて。相手を倒そうと思っていたわけじゃない。自分よりも大きなものにぶつかることで、我が身をボロボロにするまで立ち向かっていくことで、何かを吐き出そうとしていた昔の自分。不器用過ぎた子ども。 いや、今だってほんとうは変わらない。だけど、今の彼にはそれすらも出来ない。 (僕が・・・怒りに身をまかせて行動したりしたら・・・) 何もかも壊してしまう。自分の体は少しも傷つけることなく。破壊しようと思えば、世界だって壊せるかもしれない。彼がそうしたいと思いさえすれば。もちろん、そんなことは「ありえない」。あってはならないことなのだけど。 だからと言って、ふだんあえて腹を立てないように努力しているわけではない。 執着がないと言うか、特に何にも感慨がないと言うか。 フランソワーズとのことで、いくらからかってもちっとも怒らないジョーに、ときどきジェットはあきれたように言った。 「おまえ・・・何でそんなに淡々としてるんだ?」 悟りを開いちまってるみたいで、おもしろくねえな、と彼はつまらなさそうに肩をそびやかした。 実際、闘いのない日常では、特に彼が腹を立てるようなことなど何もなかった。今は、彼の人生の中で一番穏やかな時間かもしれない。惨憺たる戦闘の日々と、この機械の体と引き換えに、彼が生まれて初めて得た安らぎ。 でも、それは彼女がいればこそなのだ。 (僕は・・・今、どうかしてる) 公園の隅のベンチに腰を下ろし、ジョーは溜息をついた。 こんなにイライラしている理由(わけ)。それはちゃんと判っていた。 店を取り巻く行列は、10時が近づくにつれて、ますます膨れ上がっていった。徹夜組はもちろん、家族総出で朝から並んでいる人も、みんなお目当ては彼女だ。1家7人でやってきて、合計10個のケーキを買っていった人もいる。写真撮影や握手を求められるたび、フランソワーズは嫌な顔一つせずそれに応じていた。 もっとも今日は、ケープをはずして、という勇気ある一言を口に出せる客はいないようだ。すぐ隣で、目つきの悪いスノーマンが睨みを利かせているのだから。 それでも―――ジョーはヒヤヒヤしっぱなしだった。 「はい、これはオマケよ!」 小さな子どもにキャンディーを手渡そうと、フランソワーズは中腰になって屈みこんだ。 「う、うわっ!!!」 まずい!そのポーズは・・・前も、後ろも危険すぎる!当然、店内はフラッシュの洪水。 「フ、フランソワーズ!!あの、アブナイよ!う、後ろだって・・・」 倉庫の冷蔵庫からケーキを運び出していたジョーは思わず叫んだ。 「え?」 怪訝な顔で、彼女はジョーを振り返った。 「どうして?後ろに何か、ある?」 「いや・・・そうじゃなくて・・・その・・・」 どうしてうまく言えないんだろう。 君にこんな格好をさせたくない。今すぐ隠してしまいたい。僕以外の誰の目にも触れないように。 そう言いたいのに。 もじもじしているうちに、彼女は首をかしげながら向こうに行ってしまった。 客にケーキを渡しながら、フランソワーズと拓人は楽しげに話をしている。 それをぼんやりと眺めていたジョーは、ふと心に浮かんだ思いに、愕然とした。 ―――誰かが、君のことを好きになるかもしれない。 今まで考えてみたこともなかった。いや、なかったことのほうがおかしいのだ。 なのに――― (僕は、君が僕のそばにいてくれることを・・・当たり前だと思ってた) 何の根拠もない。そう、僕たちは何も約束などしたわけでもない。 よく考えてみれば、いや考えるまでもなく、約束どころか・・・僕は何も君に伝えていない。 君がその目で、僕を見つめてくれるだけでいいと思ってた。 何も言う必要などないと思ってた。 なぜなら、僕は今以上に君を幸せにすることなど出来ない。このありふれた日常が精一杯だから。 でも―――他の誰かが君のことを好きになったって不思議じゃない。 そして誰かが君を幸せにしようとさらって行ったとしても、僕には取り返す権利などない。 もし君が、今以上に幸せになりたいと望んだら、僕はどうすることも出来ない。もちろん、引き止めることも。 ジョーの耳にジングルベルが空しく響いた。 昼近くになり、ますます訪れる客が増えてきた。 ひょうきんなジェットのトナカイの呼び込みも好評。小さい子どもが彼と一緒に写真をとりたがった。「オジサン」よばわりされ、朝から不機嫌なアルベルトは、苦虫をつぶしたような顔で、睨みを利かせながらレジの横に突っ立っていた。しかし、彼は彼で引っ張りだこ。妙齢の熟女たちに絶大な人気だったのだ。 「ねえ、フランソワーズ」 拓人が、そっと彼女に耳打ちをした。 「アイツら・・・いったい何者なんだ?」 「何者って・・・仲間よ。どうして?」 「まさか・・・あの中の誰かが・・・君の恋人?」 「え?」 ジョーの胸がどきり、と音を立てる。彼女は何て答えるだろう。 下を向いたまま、耳に全神経を集中させた、その時。 「あのう・・・」 ハッと顔をあげると、30過ぎの女性が熱いまなざしをジョーに送っていた。 「ケーキ買ったんですけど・・・サンタさん、写真、一緒にとってもらえません?」 彼は写真が嫌いだった。さっきから、何人断っただろう。 いや、今はそれどころではなかった。 フランソワーズがじっと拓人を見つめて何か言っている。でも聞こえない。 「あのう・・・」 「ちょ、ちょと待って!」 慌ててさえぎる。 「違うわ」 きっぱりとしたフランソワーズの言葉が、突然耳に突き刺さる。 「ふうん・・・」 拓人が納得しかねる、という表情で肩をすくめた。 ―――違うわ、か。 ベンチに座り、いまいましいサンタ帽をくしゃっと引っつかんで脱ぐと、ジョーはまた溜息をついた。 そうだよな。恋人・・・だなんてとんでもない。自分だって彼女に何も言ってないんだ。なのに彼女にどんな言葉を期待してたんだ?矛盾してる。 君はいつも僕に優しい。もちろん、僕だけにじゃなくて、みんなにも。 蒼い蒼い君の瞳を見ていると、幸せな気持ちになる。 ずっと見つめていたいと思う。 でも。 君のことが好きだ、と言っていいのだろうか?こんな僕が。 暗い眼をしている、と言われ続けてきた。お前の目を見てると、虫唾が走ると。 こんな僕の前に、君は突然舞い降りてきた。 でも僕は、いつかきっと君のその美しい瞳まで翳らせてしまいそうな気がする。 この暗い目で。 街角にあふれていた楽しげな恋人たち。 僕たちはあんなふうにはなれない。 僕には、君を幸せにすることなんて出来ないから。 ふっとジョーは顔をあげた。 誰かに見られている。 さっきから誰かがじっと自分を見つめていた。 周囲に目を凝らす。ジョーの瞳に、一筋、鋭い光が宿る。 いったい誰が? 気づかないふりで、さりげなく立ち上がる。 でも―――視線は彼を追っている。いったいどこから見てる? 何者だろう? ゆっくりと歩き始める。 だがついてくる。軽く、しなやかな身のこなし。 まさか? 足音さえ聞こえてこない。相当、軍事的訓練をつんだ相手? だが、ここは街の真ん中だ。慎重に動かねば。 背後から忍び寄ってくる影。 ぎりぎりまで引きつけて、さっと身をかわし、「敵」の背後に回りこむ。 「あれ・・・?」 薄明かりの中、間の抜けたジョーの声が響いた。 |
next page |